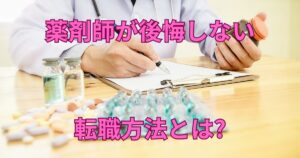【療養型病院】とは?…「医療」か「介護」で選ぶ看護師の仕事内容

もし求人ページに、「療養型病院」で働く看護師の仕事内容が次のように書かれていたら、あなたはどう判断しますか?
| 「療養型病院」における看護師の仕事内容(治療の急性期を終えて慢性期に入った患者の日常生活を長期でサポート) |
| (一日のスケジュールに沿った個別業務の例) 夜間勤務者からの引継ぎ➡ バイタルサインの測定 ➡ 入浴・体拭き ➡ リハビリ ➡ 投薬・管理 ➡ 患者の食事 ➡ 医師の診療の補助 ➡ 点滴・床ズレ処置 ➡ レクリエーション ➡看護記録・夜間勤務者への引継 |
”「医療」と「介護」両方の役割があるってこういうことなんだ”と思ったあなた →ちょっと待って!仕事の重点をどちらに置くかを考えることが先です。
漠然と捉えていると、「医師の右腕として医療に携わっていくはずが、介護ばかりやらされる」ということになりかねません。
一方、”それって「療養型病院」だけに限った話ではないんじゃないの?「介護医療院」だってあるよね”と思ったあなた →大正解です!
少なくとも、新たな施設の存在をご存じです。施設によって「医療」と「介護」への取り組み方が違うことも、何となく感じられているのだと思います。
みなさんが「療養型病院」の意味をちゃんと把握し、新たな勤務先の仕事内容を正しく判断するためのヒントがここにあります。
悔いのない転職とするため、ぜひ一緒に考えていきましょう。
「療養型病院」という言葉の使い方に注意


もともと「療養型病院」とは、「医療療養型病院(医療療養病床)」と「介護療養型医療施設(介護療養病床)」を包括した言葉だったようです。
しかし現在の「療養型病院」は、より「医療」に重点を置いた施設になっています。「介護医療院」ができて、すみ分けが進んだからです。
おのずと、新旧の「療養型病院」という言葉が意味する内容は異なります。
しかし実際は、今でも依然として旧来の意味のまま使われていることが多く、それが正しい理解の妨げになっていると感じます。
ですので、読んでくださる方が混乱しないよう、まず「介護医療院」以前とその後で「療養型病院」の意味がどう違うのかを整理します。
区別するため、この記事では、現在のそれを「療養型病院(医療療養病床)」と表記することにしますね。
その名の通り「病院」ですから、「医療」に重点が置かれるのは自然のことだと思います。
「医療」と「介護」のすみ分け


「療養型病院(医療療養病床)」の仕事内容の前に、ちょっとだけ、どうしてこんなややこしいことになっているのか、経緯を説明しておきます。
原因は、従来の「医療療養型病院(医療療養病床)」と「介護療養型医療施設(介護療養病床)」の利用者の状況にあったようです。
どちらにも大きな差が見られず、施設の目的と違う人が利用していました。要は、「医療」と「介護」の役割分担がうまくできていなかったのです。
利用者にとって、長期療養生活を送りながら充実した医療処理や見取りの必要性が増す中で、施設にも、早急な体制の再構築が求められるようになりました。
その結果「介護療養型医療施設(介護療養病床)」は昨年3月にやっと完全廃止。「介護医療院」の創設から実に6年もの猶予期間を経てのことでした。
そして、現在は「療養型病院(医療療養病床)」と「介護医療院」に整理され、それぞれの役割を担うことになっているのです。
どちらも「医療と介護の両方」が仕事内容であることに違いはありませんが、次のようなタイプの人は「療養型病院(医療療養病床)」を選びましょう。
| 患者に長期に寄り添っていく中で、あくまで看護師として「医療」にこだわりたい。介護に割くパワーをできるだけ少なくしたい。 |
「療養型病院(医療療養病床)」を「介護医療院」と比較する
両施設を比較すると、「医療」と「介護」のどちらに重点を置いているのか、その違いがよく見えてきます。
みなさんは、求人ページ等で「療養型病院」という言葉を目にしたら、旧来の意味で使われていないかをしっかり見極めてください。
そうしないと、仕事内容の選択を見誤ってしまうかもしれません。
| 『療養型病院(医療療養病床)』(「医療療養型病院」と区別する) | 『介護医療院』 =(旧介護療養型医療施設(介護療養病床) |
| 適用される保険:医療保険(が財源) | 適用される保険:介護保険(が財源) |
| 医師の配置基準:3名以上(利用者48名につき1名) | (同左) |
| 看護師・准看護士の配置基準:利用者4名に対して1名以上 | 看護師・准看護士の配置基準:利用者6名に対して1名以上 |
| 看護補助者の配置基準:利用者4名に対して1名以上 | 看護補助者の配置基準:なし |
| 介護職員の配置基準:なし | 介護職員の配置基準:利用者6名に対して1名以上 |
| 利用対象者:入院して長期療養を行う人(要支援・要介護の未申請または申請中が2割以上) | 利用対象者:医学的管理のもとの介護が必要で長期療養を行う人(要介護4・5が8割以上) |
| 医療ケアを重視 | 介護サービスを重視 |
| 「介護医療院」ができたことで、「医療」面の充実が焦点となった。 | Ⅰ型(旧介護療養病床相当)とⅡ型(老健相当)がある。 |
仕事内容を「医療」と「介護」に区分して考える
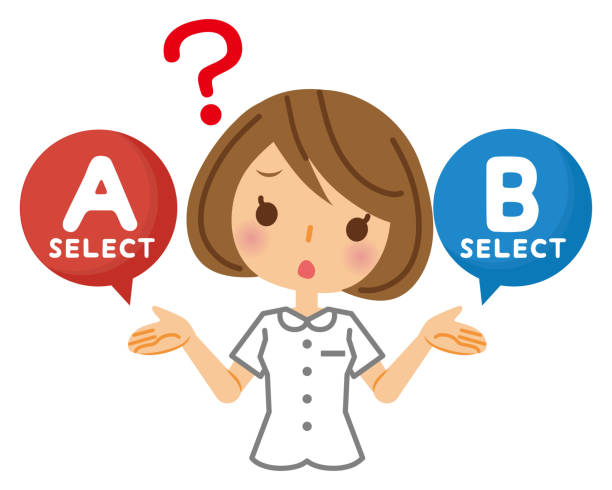
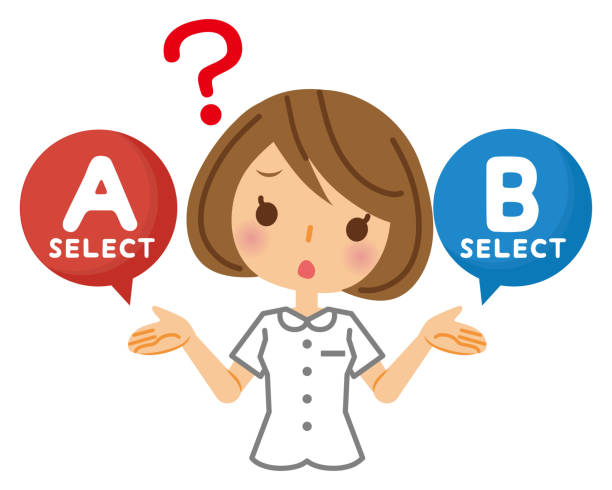
ここまでくれば、もう、冒頭の「療養型病院」は、旧来の施設を総括する漠然とした意味で使われていることがおわかりいただけますよね?
そこで、「看護師の仕事内容」を、冒頭にあげた個別業務を中心に「医療」と「介護」で区分してみます。
「医療」を志向する看護師が「介護」ばかりをやらされたりしないよう、またその逆にもならないよう、正しく判断しましょう。
「療養型病院(医療療養病床)」における看護師の仕事内容
| (一日のスケジュールに沿った個別業務の例) | 「医療」寄りの業務 | 「介護」寄りの業務 |
| バイタルサインの測定、症状の変化の把握記録 | ○ | |
| 入浴・体拭き | ○ | |
| リハビリ | ○ | |
| 投薬・管理 | ○ | |
| 患者の食事、胃ろう・経管栄養管理 | ○ | |
| 医師の診療の補助、機器の操作 | ○ | |
| 点滴・床ズレ処置、採血、注射、カテーテル | ○ | |
| レクリエーション | ○ | |
| 家族への説明と相談 | ○ | |
| 体位変換、移乗介助 | ○ | |
| 生活空間の整備 | ○ | |
| 看護師と介護士の相互連携 | ◎ | ◎ |
実際は、他の職種の人たちと一緒に働くわけですから、協力し合ってお互いの仕事をこなさなけれはならないこともあるでしょう。
考えるべきは、「医療」と「介護」にどういうバランスで向き合うか、ではないでしょうか。もう一度、前述の「施設の比較表」を眺めてみてください。
医師の配置基準は同じなのに、「療養型病院(医療療養病床)」の看護師配置基準は利用者1名につき4名と、「介護医療院」よりも厚くなっています。
これは、看護師の医療に携わる割合が「介護医療院」よりも大きいということです。逆に、介護職員の配置基準はありません。
「療養型病院(医療療養病床)」が「医療」に重点を置く「病院」寄りの施設であることがよくわかると思います。
こうした視点で転職先の仕事内容をあらかじめしっかり確認しておくことが、とても大切になってきます。
まとめ


まずは、様々な情報に含まれる「療養型病院」の意味を正しく読み取ることが大切です。
旧来の意味のまま「介護医療院」の部分だけを置き換えている記事が散見されますので、誤った情報を鵜呑みにしないように気を付けましょう。
「介護医療院」は「病院」ではないのだから、以前のように「療養型病院」に含めるのは、今となってはおかしいですよね。
もしかすると、「療養型病院」という言葉は過去に任せて、「療養型病院(医療療養病床)」に代わる新しい呼称を考えるべきかもしれません。
いずれにしても、そんなわかりにくい状況の中だからこそ、自分は「医療」「介護」のどちらに軸足を置きたいのかをしっかり考えておくことが大切なのです。
そうすれば、おのずと自分にとってのいい転職ができるでしょう。
仕事内容は「医療」「介護」の両方あれど、どちらに重点が置かれているのか、どういう人員配置なのかをちゃんと確認しておきましょう。
前述の「施設の比較表」が指針となるでしょう。
輝かしい再スタートを切ることができるよう、心からお祈りします。
転職先探しに役立つ記事なら「看護師転職サイトおすすめベスト3!絶対失敗しない選び方も紹介」
転職が決まったら真っ先に使っていただきたいのは「ナースリー楽天市場店」です。




頑張ってください。応援しています。