薬剤師が医師と関わりを深めるために明日から実践できる工夫とは?
「もう長くこの病院で働いているのに、医師と薬剤師の間でギクシャクしている気がする」
「『疑義照会』をするたびに、相手の態度が冷たく感じてしまう」
そんな経験はありませんか?
経験を重ねてきたからこそ、現場のちょっとした空気の変化や関係性の違和感に敏感になりますよね。
それでも、忙しい毎日の中で「どう改善したらいいのか分からない」と悩まれているのではないでしょうか。
この記事では、現場で苦労しながら関係改善に成功した事例をご紹介します。
また、経験豊富な薬剤師さんだからこそ活かせる視点をもとに、すぐに試せる小さな工夫もまとめました。
読み終わる頃には、「明日から少しずつやってみよう」と感じてもらえるはずです。
Contents
なぜ医師と薬剤師はすれ違うのか?──知らず知らずの認識の相違に注意
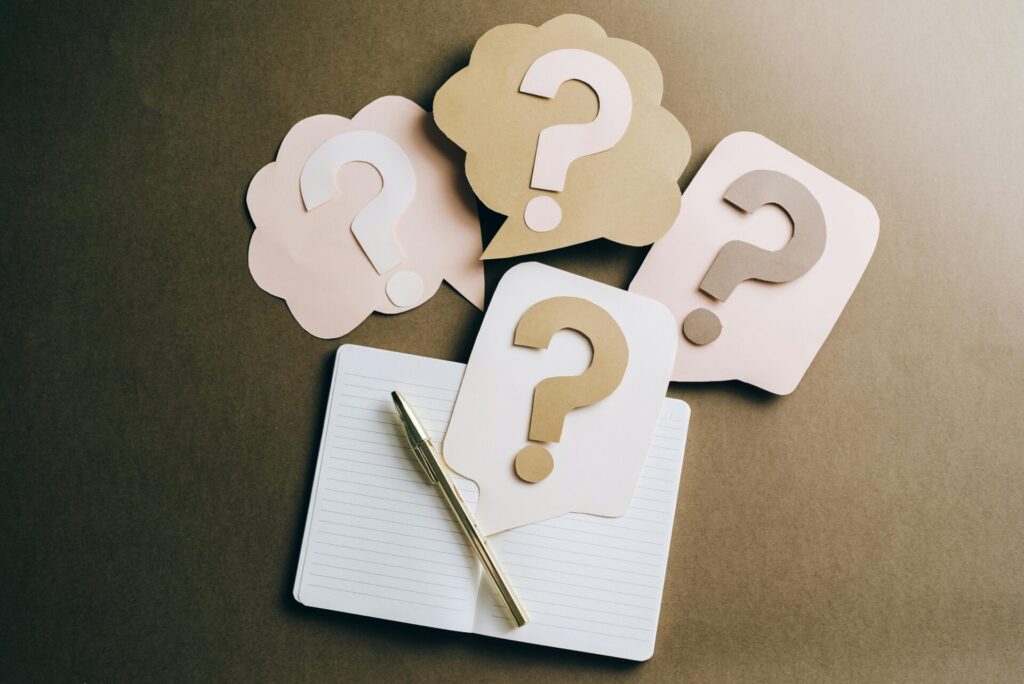
医師と薬剤師のすれ違いはどこから生まれているのでしょうか。
- 医師は、診断と治療の全体設計を担う立場
- 薬剤師は、安全性と服薬の最適化に責任を持つ立場
それぞれの立場や役割の違いが、時にすれ違いの元になっていることがあります。
薬剤師さんが疑問を感じながらも照会を控えた結果、患者さんのリスクにつながってしまった事例がありました。
こうした“遠慮”や“誤解”が積み重なり、知らず知らずのうちに溝ができてしまうのです。
疑義照会は「指摘」ではなく「医療チームの質を高める大切な連携作業」

疑義照会に対して、「面倒だな」と感じる医師もいるかもしれません。
それは、疑義照会が単なる指摘となっているからではないでしょうか。
本来は、「患者さんの安全を守るために医療チームで協力する重要な連携作業」です。
しかし現場では、こんなすれ違いが起こりやすいのです。
- 医師は「自分の判断を疑われた」と感じてしまうことがある
- 薬剤師は「ただ確認したいだけなのに、冷たい反応をされる」と感じることがある
- 忙しい中での照会が重なり、「またか」と受け取られてしまうことがある
こうした小さなすれ違いが重なり、疑義照会が“指摘の場”として受け止められてしまうのです。
その結果、「本当は確認した方がいい」と思っても遠慮してしまう…。
そんな状況が生まれることもあります。
疑義照会の本来の目的は「相手を正すこと」ではなく、「チームとして最善を探ること」です。
しかし、この認識のズレが放置されると、医師と薬剤師の間に“見えない壁”ができてしまうのです。
「報告・連絡・相談(報連相)」の質で関係性は大きく変わる

報連相が、ただの業務連絡となってはいないでしょうか。
これまでにも無数の報告・連絡・相談を重ねてこられたことと思います。
しかし、忙しさや慣れから、つい「伝えること」だけに意識が向いてしまうことがあります。
例えば、
- 要件だけを伝えてしまい、相手の状況に配慮できていない
- 「処方変更お願いします」と言い切る形になり、命令的に聞こえてしまう
- 忙しい医師に長い説明をしてしまい、要点が伝わりにくくなる
こうしたやり取りが積み重なると、「冷たい」、「協力的でない」といった印象が生まれます。
その結果、お互いの距離が広がってしまうのです。
報連相は、情報伝達の場であると同時に、“信頼を積み重ねるためのコミュニケーション”でもあります。
この意識のズレが、関係性のすれ違いを生む原因になるのです。
連携がうまくいく現場の共通点──「顔の見える関係づくり」

成功している病院には、こんな共通点があります。
- 定期的なミーティングで意見交換をしている
- 薬剤師が病棟に足を運ぶ機会が多く、自然と顔を合わせる習慣がある
- 「患者さんにとって最善を尽くす」という目的がチームで共有されている
ミーティングは、最初は形式的でも構いません。
回を重ねるうちに、少しずつ本音が出やすくなり、建設的なやり取りへと変わっていきます。
また、「お疲れさまです」、「今日もよろしくお願いします」といった声かけも、連携の土台になります。
こうした“あたりまえのこと”を丁寧に積み重ねていくことが、結果的にチームとしての力を高めてくれます。
小さな工夫で医師と薬剤師の関係を改善する方法

関係改善は大きな改革だけでなく、毎日のちょっとした行動の積み重ねも大切です。
むしろ、日々の何気ない一言や、ちょっとした姿勢の変化が、後々大きな違いを生むことがあります。
現場で信頼を積み重ねてきたからこそ「どう伝えればいいか」、「何が響くか」が自然と身についています。
そうした現場の機微に気づけるのも、大きな強みです。
その感覚を生かして、ほんの少しだけアプローチを変えてみる。
それだけで、関係性の質が大きく変わることもあります。
ここでは、明日から無理なく始められる5つのアクションをご紹介します。
特別な準備もテクニックもいりません。
これまでの経験に、ほんの少しの工夫を加えるだけで、確かな変化を生むヒントになるはずです。
① 報告や提案の最後に「ありがとうございます」を添える
これまでの経験から、丁寧な言葉遣いが対人関係に及ぼす影響は、実感されていることと思います。
「お忙しい中すみません、ありがとうございます」
その一言があるだけで、相手の受け取り方が柔らかくなりますし、自分の気持ちの余裕にもつながります。
小さな言葉ですが、信頼関係の土台となる“相互の敬意”を表す重要な表現です。
② 提案は「〇〇かもしれませんが、いかがでしょうか?」と相談形式にする
専門知識に基づいた発言は、強く響きすぎてしまったと感じた経験があるのではないでしょうか。
そんなときは、提案のトーンを相談ベースに変えるだけで、ずいぶん伝わり方が違ってきます。
「こうしたリスクがあるかもしれませんが、ご確認いただけますか?」
「こちらの方がより安全かと考えたのですが、いかがでしょうか?」
上記のように相手を尊重しつつ、プロとしての意見を伝えてみる。
このバランス感覚は、現場をよく知る薬剤師さんだからこそ持ち得るものではないでしょうか。
③ 「患者さんのために」と共通の目的を明確にする
「この提案は、患者さんの○○に配慮してのことです」
こうした言葉を添えるだけで、相手に「否定された」と思わせずに済みます。
チーム医療においては、「自分たちは同じ方向を向いている」という意識の共有がとても大切です。
その一言が、相手に安心感を与え、信頼の架け橋となります。
④ 朝の挨拶やちょっとした雑談を大切にする
「おはようございます」、「今日はどうでしたか?」
そんなやりとりがあるだけで、医師との心理的距離はぐっと縮まります。
とくに病棟常駐がない、顔を合わせる機会が限られている場合は、関係づくりが難しくなりがちです。
だからこそ、ちょっとした“雑談力”が関係構築のカギになります。
気持ちよく話せる関係性は、いざという時の相談のしやすさにも直結します。
雑談は、実は“最も実用的な関係づくりの技術”なのではないでしょうか。
⑤ カンファレンスやミーティングで積極的に質問や意見を出す
カンファレンスやミーティングは、薬剤師としての視点を伝えるまたとない場です。
ここでの発言が、医師の信頼や期待を引き出すきっかけになることも少なくありません。
「この薬を選択された理由を教えていただけますか?」
「別の薬剤との相互作用の観点から、こちらも一案かと考えましたが、いかがでしょうか?」
発言のハードルは高く感じるかもしれませんが、日常のちょっとした気づきを言語化するだけでも十分です。
実務に精通した薬剤師さんが言葉にして伝えることで、チーム内での存在感も自然と高まります。
まとめ
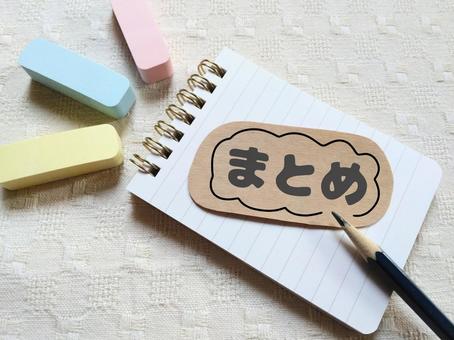
関係改善は「少しの気遣い」と「積み重ね」が大切です。
- 医師と薬剤師のすれ違いは、立場や認識の違いから起きている
- 疑義照会は「患者さんの安全を守るチーム医療の重要な工程」と考える
- 報連相は「伝え方次第」で関係が大きく変わる
- 成功している現場は「継続的なコミュニケーション」と「顔が見える関係性」がある
- 小さな行動の積み重ねが、職場の雰囲気と連携の質を変える
長く現場に携わってきたからこそ、変えたい空気があると思います。
必要なことは、「長年の関係にちょっとした彩りを入れてみる」ことではないでしょうか。
この小さな変化で、現場は驚くほど動き出します。
この記事が、薬剤師さんのチーム医療の質向上に役立つことを願っています。
もしも…
実践してみたけれど難しかった、もっと自分に合った環境があるのでは?
こんな風に考えた方は、転職も1つの選択なのかもしれません。
求人だけじゃない、薬剤師さんの“理想の環境”を選べる転職サイト“お仕事ラボ”はこちら
薬剤師転職サイトおすすめ2選!ランキング常連3社との比較はこちら
より良い環境で、チーム医療の一員としてさらに活躍できる未来を応援しています。


